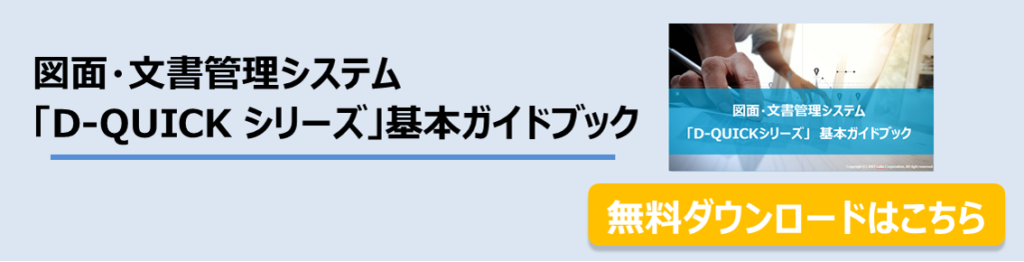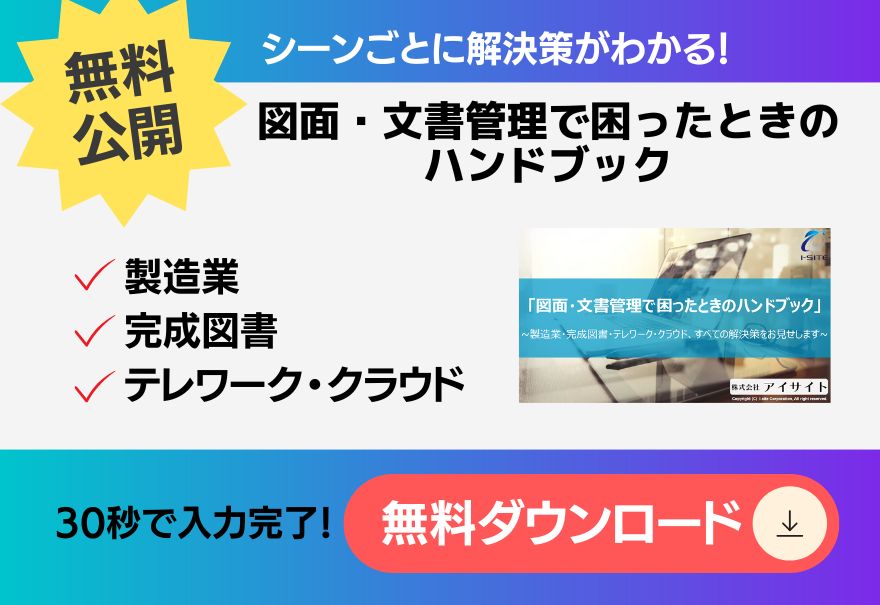企業には他社との差別化ポイントとして他社にないノウハウがあるのではないでしょうか。他社には真似ができないノウハウこそ、企業価値を高める最大の要素です。そのノウハウを共有化し属人化から解決する取り組みとして「ナレッジマネジメント」があります。本記事では、ナレッジマネジメントとコンテンツ管理との違いや組織で情報共有できる方法についてご紹介いたします。
ナレッジマネジメントとは?
他社との差別化ポイントとして、価格が安い、品質が良いなども重要ですが、一番強いのは他社にないノウハウがあることです。他社には真似ができないノウハウこそ、企業価値を高める最大の要素です。
しかし、そのノウハウへの取り組みが個人であればあるほど、そのノウハウが属人化され、ノウハウの継承問題が発生します。このような問題を解決する取り組みとの解決策として考えられてきたのが「ナレッジマネジメント」です。
ナレッジマネジメント(Knowledge Management)とは、KMとも呼ばれ、組織内の知識を効果的に活用・共有・蓄積するためのプロセスや取り組みのことをいいます。個人やチームが持つ知識や経験を集約し、組織全体で共有することで、意思決定の質を向上させたり、業務の効率化を図ったりすることができます。
1.ナレッジマネジメントの目的
ナレッジマネジメントには以下の目的があります。
○知識の共有
個々の社員が持つ暗黙知を形式知に変え、組織内で共有する
※暗黙知:経験や直感、感覚など、言語化・形式化しにくい知識
形式知:文書、マニュアル、データベースなど、言語化され組織的に共有できる知識
○業務効率化
重複作業の削減や、過去の成功事例・失敗事例を活用することで、効率的な業務を実現する
○イノベーション促進
異なる知識を結びつけ、新たなアイデアや価値を創出する
○属人化の解消
個人に依存しない業務体制を構築し、退職や異動による知識の喪失を防ぐ
2.ナレッジマネジメントのプロセス
○知識の取得
個人やチームからの情報を集め、組織の資産として確保する。
○知識の共有・伝達
適切なツールやシステム(例:社内ポータル、データベース、SNS)を使い、組織内で共有する。
○知識の応用
業務の問題解決や意思決定に活用する。
○知識の蓄積
過去の事例や教訓を記録し、将来の業務に活用する。
ナレッジマネジメントとコンテンツ管理の違い
情報共有を実現する方法として、コンテンツ管理もあります。ナレッジマネジメントとコンテンツ管理の違いは、どちらも情報やデータを扱いますが、目的や範囲、対象が以下の様に異なることです。
1.目的の違い
【ナレッジマネジメント】
・個人や組織の知識(暗黙知や形式知)を効果的に共有・活用し、業務改善や意思決定、イノベーションを促進する。
・目標は知識資産の活用と組織力の強化
【コンテンツ管理】
・ウェブサイトやアプリ、社内ポータルなどのプラットフォームで使用するコンテンツ(テキスト、画像、動画など)を効率的に管理・公開する。
・目標は、最新で正確な情報の提供やユーザーエクスペリエンスの向上。
2.管理対象の違い
【ナレッジマネジメント】
暗黙知と形式知の両方を扱う。
(例)ベストプラクティス、問題解決のノウハウ、社員間の情報交換
【コンテンツ管理】
形式化されたコンテンツ(記事、マニュアル、製品情報、広告素材など)が主な対象。
(例)Webページ、ブログ記事、動画、PDFファイル
3.使用するシステムの違い
【ナレッジマネジメント】
社内ポータルやナレッジベース、Wiki、Q&Aシステムなどが多い。情報の共有やコラボレーションを促す機能が重視される。
(例)Confluence、SharePoint、Notion
【コンテンツ管理】
ウェブサイトやアプリのコンテンツを構築・管理するためのシステム。公開フローやバージョン管理に特化
(例)WordPress、Drupal、Adobe Experience Manager
4.運用プロセスの違い
【ナレッジマネジメント】
知識の収集、共有、応用、更新を通じて組織全体の学習を促進
(例)プロジェクト終了後の振り返り会で得られた知見をデータベースに記録
【コンテンツ管理】
コンテンツの作成、編集、レビュー、公開、廃止といったライフサイクルを管理
(例)新製品リリース時のプレスリリースをCMSで公開・更新
5.実務的な違い
【ナレッジマネジメント】
社員のスキルや経験を共有し、長期的な組織知の蓄積に重きを置く
(例)熟練エンジニアのノウハウを若手に伝える
【コンテンツ管理】
消費者や社内外のユーザー向けに、一貫性のあるメッセージを発信し、ブランド価値を向上させる
(例)製品サイトのFAQページを管理して常に最新情報を提供。
結論として、ナレッジマネジメントは、組織内の「知識」の管理と活用に焦点を当て、主に内部のプロセス改善を目的とするのに対して、コンテンツ管理は、主に「コンテンツ」の作成・運用・公開を管理し、顧客やユーザーとのコミュニケーションの円滑化を目的とします。
それぞれの役割は異なりますが、両者が連携することで、たとえばナレッジマネジメントの成果をコンテンツ化し、外部向けに発信するなどの相乗効果も期待できます。
お客様の声から、もっと業種別に学んでみよう!
製造業の図面・文書管理 自治体の完成図書管理
D-QUICK導入事例集
ナレッジマネジメントのメリット
1.業務効率の向上
知識やノウハウを組織全体で共有することで、重複作業を減らし、迅速な意思決定を支援します。
(例)過去のプロジェクトの失敗例や成功例を参照し、類似案件での効率的な対応が可能になる
2.イノベーションの促進
異なる部署やチームの知識が共有されることで、新しいアイデアや製品開発につながる可能性が高まります。
(例)営業部門の顧客インサイトを開発チームが活用し、ユーザー志向の製品を開発
3.属人化の解消とリスク低減
個人の経験やスキルが組織全体に蓄積されることで、特定の社員に依存しない体制を構築し、退職・異動によるリスクを軽減します。
(例)熟練社員のノウハウをデータベースに記録し、新人教育に活用
これにより、組織の競争力が向上し、持続的な成長を支える仕組みが整います。
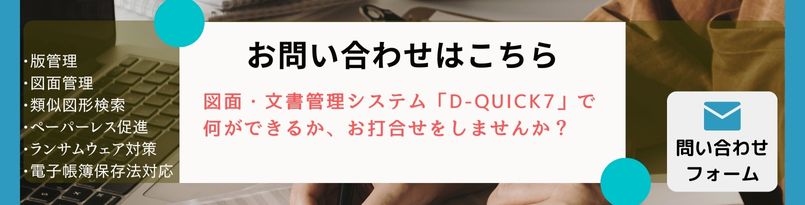
まとめ
「ナレッジマネジメントとは?情報の属人化を解決するシステムへ」と題して、ご紹介してまいりました。企業の運営にはITを利用したシステムにより情報を共有し運営していますが、システムの情報は2割しかないと言われています。残り8割は、ドキュメント(電子文書、紙文書、メール)と言われていますが、実は企業内の社員が頭の中で持っているノウハウは含まれていません。
企業内のあらゆるノウハウが全てシステム化、文書化されている企業はほとんどなく、日々社員が取り組んでいる活動こそが企業ノウハウなのかも知れません。
企業ノウハウをすべて明示化することは困難かもしれませんが、企業を存続させていく上で必ず必要な情報になります。そのノウハウを共有化するナレッジマネジメントへの取り組みこそが企業を支える重要な取り組みではないでしょうか?
ナレッジマネジメントへの取り組みでお困りのことがありましたら、是非アイサイトへご相談ください。
当サイトでは、「D-QUICKシリーズ」についてわかりやすく説明している資料をご用意しております。安心・安全に図面・文書管理を行うためのポイントが理解できる資料になっています。 ぜひ、ダウンロードページより資料をご覧ください。
まだ情報収集レベルで、学びを優先されたい方
「図面・文書管理で困ったときのハンドブック」~製造業・完成図書・テレワーク・クラウド、すべての解決策をお見せします~
システムやクラウドサービス等の具体的な解決策を探している方
図面・文書管理システム「D-QUICKシリーズ」基本ガイドブック
より詳しい事例を知りたい方
「製造業の図面・文書管理 自治体の完成図書管理 D-QUICK導入事例集」
版管理や採番に課題を感じている方
版管理と採番管理を解決する D-QUICK7機能ガイド
安心・安全に図面・文書管理を行うためのポイントが理解できる資料になっています。 ぜひ、ダウンロードページより資料をご覧ください。
「文書管理ノウハウ」の関連ブログ
- 建築士法の法改正に対する課題の解決策 こんな方法があったの?
- 製造業DXが進まない本当の理由 成功に導くヒントをご紹介
- 文書管理システムで実現するグローバルオペレーションの効率化
- AIで図面管理を実現する2つのキーワード セマンティック検索も解説
- 出図とは?最新版の混乱をなくす出図管理の基本と効率化のコツ
- 文書管理の原点「ドキュメント」とは?現場で活かす価値も解説
- 設計 ・ 仕様書を含む契約書管理の課題を解決する効率的な方法
- 文書管理で原本を守る 文書管理システムとファイルサーバーの違いを解説
- 製造業DXの事例 課題と推進させるポイントをご紹介
- 製造現場の未来を拓く 図面のペーパーレス化がもたらす3つの革新
- 図面管理システムで始める完成図書のデジタル化
- AIで製造業の設計業務はどう変わる?課題と対応方法を解説
- ファイルサーバと同じ操作性を持つ検索ツールで効率化!基幹システム刷新のポイントを解説
- PL法で問われる証拠力、文書管理の重要性を徹底解説
- 機密情報を守り情報漏洩を防ぐ方法 図面・完成図書はどうする?
- フォルダ検索したい!なぜ目的のフォルダが見つからないの?
- ナンバーの付け方で劇的に変わる 文書管理の業務効率アップ術
- ナレッジマネジメントとは?情報の属人化を解決するシステムへ
- バックオフィスの文書管理の課題とは?システムが必要な理由を解説
- 書類の電子化をしよう!方法と注意点、事例をご紹介