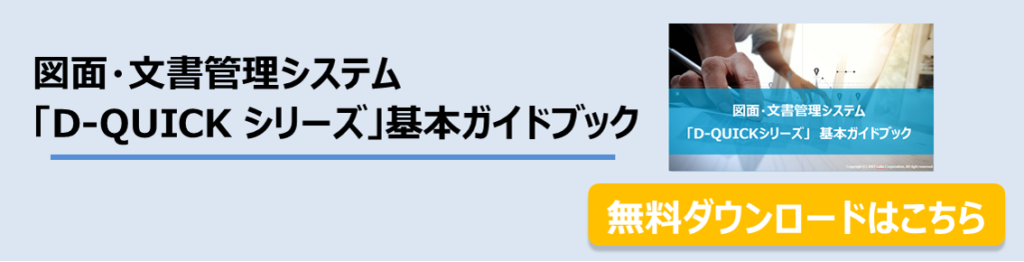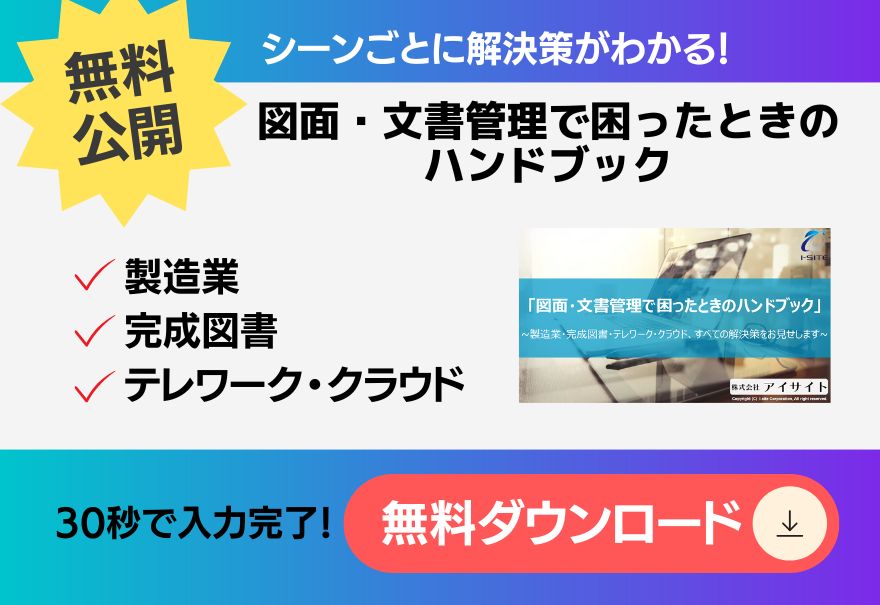製造業の多くがDXへ積極的に取り組みを進めていますが、中々その効果が出ないと感じているというお声をよく耳にします。その原因と課題は何なのか、他の企業はどんな取り組みをしているのか、知りたい方も少なくないと思います。そこで、製造業DXの事例を中心に推進させるポイントをご紹介していきます。
製造業DXの現状と課題
日本の製造業は大企業より中小企業の方が圧倒的な数を占めていますが、中小企業の製造業では中々DXが進んでないと言われています。この原因は、製造業の企業文化という固定観念とITシステムの規模の差にあるのではないでしょうか。
中小企業では、DXへの資金導入の余裕がないため、個別部門ごとにシステムの最適化を優先してしまい、製造現場の現実と収集・分析したデータが一致せず、企業全体の情報管理・データ管理の最適化が進んでいません。
従って、AIやIoT、クラウドなど最先端のシステムを導入しても、基盤となる各工場の製造ライン活用や連携が限定的になりDXを実施しても思うような成果が出せないのです。
DXは「デジタルテクノロジーを取り入れる事でビジネスの変革を図る」ことと定義されていますが、我が国では大企業と中小企業との間のいわゆる「デジタル・ディバイド(情報格差)」が懸念されています。
情報ITを利用する能力、およびアクセスする機会を持つ者と持たざる者との間に情報格差が生じることが個人経営の企業や中小企業の製造現場によく見られます。
デジタル・ディバイドが生じる原因は、ブロードバンド整備にかかるコストや、人材不足、地方の少子高齢化など複合的な問題が絡み、すぐに解決できるものではありませんが、原因を追求し一つずつ解決に向けて前進する必要があります。
経済産業省では、DXの推進として、経営のあり方、仕組みを見直し、DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築を定義しています。
DXへ取り組むために
DXと混在する言葉で、IT化という言葉があります。IT化は、自社の業務をIT技術によって効率化・自動化して課題を解決することであり、DXの目的である業務の課題を解決して新たなビジネスモデルを生み出す事とは異なります。
DXの実現にIT技術は必須要件ですが、業務改善と新たなビジネスの創立をしっかり理解する必要があります。DXを本格的に推進していくためには、以下の問題点をクリアする必要があります。
・最新デジタル技術に詳しい人材が不足している
DX推進にはAIやIoTといった最新の技術に詳しい人材や、デジタル技術を活かした新たな事業・サービスを企画できる人材が必要です。
・個別最適になっている
多くの中小企業が、事業部ごとにそれぞれで最適な異なるシステムを設置した為、企業全体のデータ管理や連携ができずDXが思った通りに進まない状況にあります。
・既存システムの老朽化
製造業ではレガシー問題を抱えていることに気づきにくい状況にあります。長年に渡りシステムのメンテナンスを定期的に行わず日常的に活用できている間は、レガシーであることを自覚されません。
既存システムの運用に何度も問題が発生しシステムを見直す事態になって初めてレガシー問題を抱えていることに気づくという特徴があります。この状態から解消するには長い期間と大きな費用を要するうえ、手戻りのリスクもある中で、根本的にシステム刷新するのはかなり大変です。
お客様の声から、もっと業種別に学んでみよう!
製造業の図面・文書管理 自治体の完成図書管理
D-QUICK導入事例集
DXを推進させるポイント
経済産業省が「デジタルトランスフォーメーション銘柄2023」で記載しているDXを推進するためのポイントは以下のとおりです。
(経営ビジョン)
・世の中のデジタル化が⾃社の事業に及ぼす影響(機会と脅威)を明確なシナリオで描けていること
・経営ビジョンの柱の⼀つにIT/デジタル戦略を掲げていること
(戦略)
・経営ビジョンを実現できる変⾰シナリオとして、戦略が構築できている
・IT/デジタル戦略・施策を合理的かつ合⽬的な予算配分がなされている
・データを重要経営資産の⼀つとして活⽤している
(組織・⼈材・⾵⼟)
・IT/デジタル戦略推進のために各⼈(経営層から現場まで)が主体的に動けるような役割と権限が規定されている
・社外リソースを含め知⾒・経験・スキル・アイデアを獲得する組織能⼒を有している
・デジタル戦略推進のために必要なデジタル⼈材の定義と、その確保・育成/評価の⼈事的仕組みが確⽴されている
・必要とすべきIT/デジタル⼈材の定義と、その獲得・育成/評価の⼈事的仕組みが確⽴されている
・⼈材獲得・育成について、現状のギャップとそれを埋める⽅策が明確化されている
・リスキリングやリカレント教育など、全社員のデジタル・リテラシー向上の施策が打たれている。その中では、全社員が⽬指すべきリテラシーレベルのスキルと、⾃社のDXを推進するための戦略を実⾏する上で必要となるスキルとがしっかりと定義され、それぞれのスキル向上に向けたアプローチが明確にされている
・経営トップが最新のデジタル技術や新たな活⽤事例を得た上で、⾃社のデジタル戦略の推進に活かしている
・全社員のIT/デジタル・リテラシー向上の施策が打たれている
・組織カルチャー変⾰の取組み(雇⽤の流動性、⼈材の多様性、意思決定の⺠主化、失敗を許容する⽂化など)
・経営戦略と⼈材戦略を連動させた上で、デジタル⼈材の育成・確保に向けた取組が⾏われている
(IT・デジタル技術活⽤環境の整備)
・レガシーシステム(技術的負債)の最適化(IT負債に限らず、包括的な負債の最適化)が実現できている
・先進テクノロジの導⼊と独⾃の検証を行う仕組みが確⽴されている
・担当者の属⼈的な努⼒だけではなく、デベロッパー・エクスペリエンス(開発者体験)の向上やガバナンスの結果 としてITシステム・デジタル技術活⽤環境が実現できている
(情報発信・コミットメント)
・経営者が⾃⾝の⾔葉でそのビジョンの実現を社内外のステークホルダーに発信し、コミットしている
(経営戦略の進捗・成果把握、軌道修正)
・経営・事業レベルの戦略の進捗・成果把握が即座に⾏える
・戦略変更・調整が⽣じた際、必要に応じて、IT/デジタル戦略・施策の軌道修正が即座に実⾏されている
(デジタル化リスク把握・対応)
・企業レベルのリスク管理と整合したIT/デジタル・セキュリティ対策、個⼈情報保護対策やシステム障害対策を組織・規範・技術など全⽅位的に打っている
DX実現の流れ
DXは、以下の3つの過程を経て実現できます。
(過程①:デジタイゼーション)
データ化できていないものをデータにする
【前】Wordで作成した文書を稟議で回覧してハンコを押す
↓
【後】Wordのままメールで回覧する(ペーパーレス)
(過程②:デジタライゼーション)
デジタル化プロセスを含めたデジタル化
【前】Word文書をメール送信してそれぞれがチェックして結果を返信
↓
【後】クラウドにUPしてチェックマークを入れる、確認も簡単
(過程③:DX)
高度な自動化、これまでにない利便性
クラウド承認システムを新規事業として外部へサービス展開
自社ビジネスモデルの変革にとどまらず顧客行動様式まで変える事に成功
DX取組みの流れ
DXの検討・進め方は、基本的に一般業務改善と同じです。
① ビジネスモデル図の作成
DXのゴール=新たなビジネスプランを見つけること
② 業務上の課題を洗い出す
下記③ののプロセス毎に関係部署へヒアリングし課題の洗い出し
③ デジタル化すべき業務の洗い出し
課題からデジタル化のアプローチ方法を明確化
④ データの流れを把握する
データの流れをシステムマップへ
⑤ データ活用の可能性を考える
実現すべき理想のビジネスを描いて、理想を具現化
⑥システムマップとのギャップを明確化
理想と現状を比較して改善ポイントを検討
⑥ 生産性を上げるシステム改善
システム改修の成果を具体的にして計画書へ盛り込み
⑦ 実施した効果を計測する
改善効果を確認する体制の確立し、計測
⑨DX推進チームを作る
体制図と責任分担を明確化
⑩スケジュールの作成
いつ成果が出るのか目標となる期日を設定
⑪DXの費用対効果を見積る
費用対効果を試算
DX成功事例の紹介
事例① :Netflix
・創業時はDVD配送レンタルのサービスを展開
・2012年からブロードバンド環境が整った事を背景にストリーミング配信を開始
・コストの掛かるDVDレンタルサービスをIT化でコスト削減
・サブスクリプションにより利益率と売上拡大を実現
・事業やサービスが元来の姿と異なる特性を持ち合わせたビジネスモデルへ変革
事例② :Uber
・Uber Technologies=Uber Eatsが有名
・車での移動を求めるユーザがスマホアプリなどで近くにいる契約車を手配し、タクシーよりも安価な料金で目的地まで運んでもらえるサービスを展開
・モバイル環境での配車アプリ提供(GPS連携しリアルタイム車両とユーザの位置を把握)し、スマート決済などから構成されるサービスを展開してDXを実現
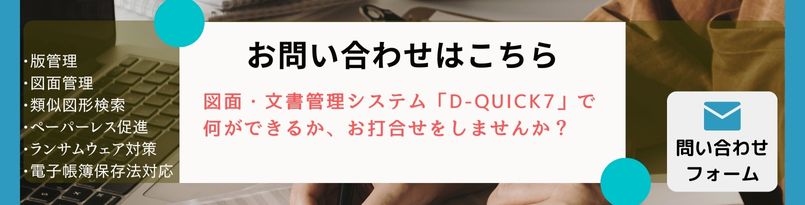
まとめ
DXの実現は、単に業務のやり方をIT化するだけではありません。ITの活用に加え、ネット環境やAIを組み合わせて今までにない新しいサービスを展開する事で実現することができます。
お客様が望む理想と現実とのギャップを洗い出す事が重要ですが、その為にはどんなIT技術を利用すればギャップを埋められるか最新のIT知識と発想力が大事です。また、最近では、最新のIT知識がなくてもChatGPTやCopilotなどのAIチャットを利用して相談すれば、AIが最新情報を踏まえたヒントを得る事も可能です。
当サイトでは、「D-QUICKシリーズ」についてわかりやすく説明している資料をご用意しております。安心・安全に図面・文書管理を行うためのポイントが理解できる資料になっています。
ぜひ、ダウンロードページより資料をご覧ください。
まだ情報収集レベルで、学びを優先されたい方
「図面・文書管理で困ったときのハンドブック」~製造業・完成図書・テレワーク・クラウド、すべての解決策をお見せします~
システムやクラウドサービス等の具体的な解決策を探している方
図面・文書管理システム「D-QUICKシリーズ」基本ガイドブック
版管理や採番に課題を感じている方
版管理と採番管理を解決する D-QUICK7機能ガイド
より詳しい事例を知りたい方
「製造業の図面・文書管理 自治体の完成図書管理 D-QUICK導入事例集」
「文書管理ノウハウ」の関連ブログ
- 製造業DXが進まない本当の理由 成功に導くヒントをご紹介
- 文書管理システムで実現するグローバルオペレーションの効率化
- AIで図面管理を実現する2つのキーワード セマンティック検索も解説
- 出図とは?最新版の混乱をなくす出図管理の基本と効率化のコツ
- 文書管理の原点「ドキュメント」とは?現場で活かす価値も解説
- 設計 ・ 仕様書を含む契約書管理の課題を解決する効率的な方法
- 文書管理で原本を守る 文書管理システムとファイルサーバーの違いを解説
- 製造業DXの事例 課題と推進させるポイントをご紹介
- 製造現場の未来を拓く 図面のペーパーレス化がもたらす3つの革新
- 図面管理システムで始める完成図書のデジタル化
- AIで製造業の設計業務はどう変わる?課題と対応方法を解説
- ファイルサーバと同じ操作性を持つ検索ツールで効率化!基幹システム刷新のポイントを解説
- PL法で問われる証拠力、文書管理の重要性を徹底解説
- 機密情報を守り情報漏洩を防ぐ方法 図面・完成図書はどうする?
- フォルダ検索したい!なぜ目的のフォルダが見つからないの?
- ナンバーの付け方で劇的に変わる 文書管理の業務効率アップ術
- ナレッジマネジメントとは?情報の属人化を解決するシステムへ
- バックオフィスの文書管理の課題とは?システムが必要な理由を解説
- 書類の電子化をしよう!方法と注意点、事例をご紹介
- 文書管理されるファイルは保存?格納?違いや意味を理解してみよう