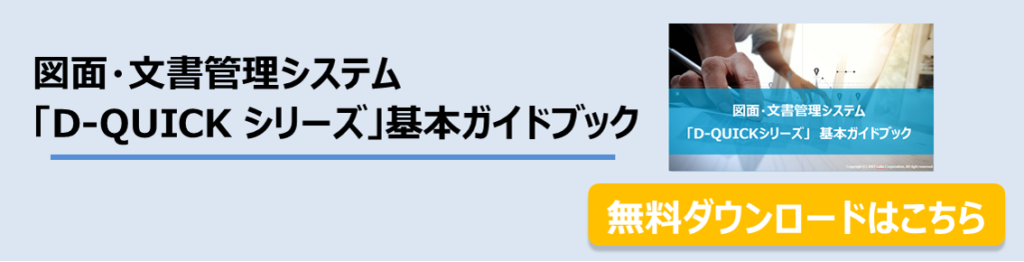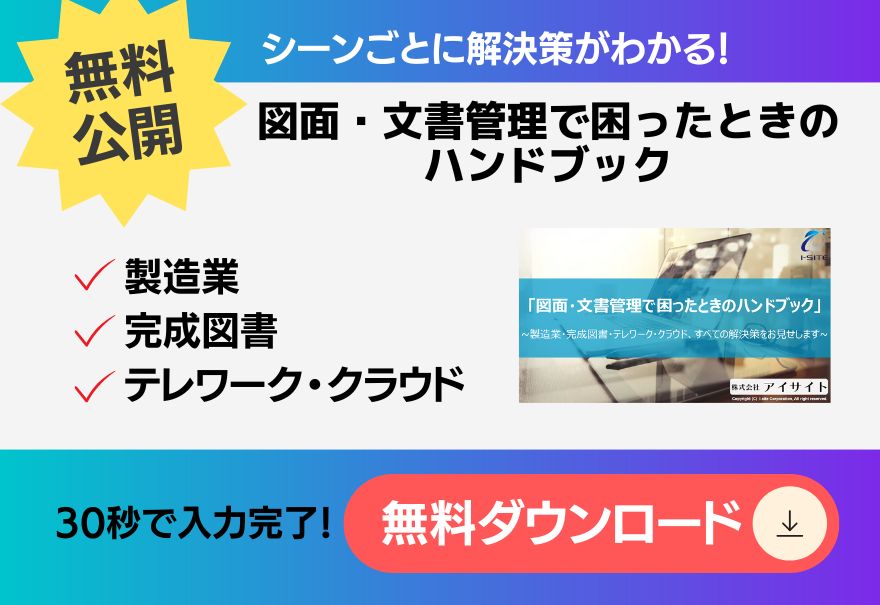製造業において設計業務は製品の性能や信頼性はもちろん、製造コストや納期といったビジネスの根幹に直結する、極めて重要な工程です。設計の良し悪しが、その後の製造プロセス全体に大きな影響を及ぼすため、これまでは長年の経験を持つ設計者自身のノウハウと勘が重視されてきました。
しかし近年、製造業でもAIの導入が進み、設計分野でもその活用が注目されています。特に、自然言語処理や機械学習といった技術を用いたAIツールが登場し、設計者の業務を支援する取り組みが広がりつつあります。本記事では、製造業における設計業務にどんなAIが活用できるのか、また実際にAIを活用することによる利点や懸念点などを分かりやすく紹介していきます。
AIが活用できる設計業務
それでは実際に、設計現場ではどんなAIが活用できるのかを以下ご紹介します。
1. ドキュメントの検索
膨大な図面、マニュアル、設計仕様書、法規文書などから、必要な情報をすばやく探すことは、円滑に業務を進める上で重要です。通常、ドキュメントはPCやファイルサーバーで保存しており、ファイル名で検索することが多いと思います。
しかし、AIを搭載したドキュメント管理システムを利用することで、図面の形状から類似図面を探したり、図面同士を比較して差分を表示したり、様々な検索が可能になっています。また報告書や議事録などのドキュメントは、AIを使った要約を行うことで、概要を素早く把握できます。
2. 設計補助・アイデア提案
構造設計や機構設計の初期段階で、条件を入力することで複数のアイデアを提示するAIツールも登場しています。ChatGPTなどのAIツールは図面そのものを描くことはできませんが、設計の方向性を整理したり、設計上の懸念点を洗い出したりする補助として活用できます。
また新しいアイデアのブレインストーミングや、既に話し合ったアイデアのジャンル分けや整理もしてくれます。
3. ドキュメント生成・自動化
設計業務では、図面の説明文や設計意図、検討履歴などを文書化する作業が発生します。これらの作業は時間がかかる一方で、表現にばらつきが出やすく、属人化しがちです。ChatGPTなどのAIツールを活用すれば、設計者が要点だけを箇条書きにしやすくなるので、自然な文章に整えられることができます。従って、ドキュメント作成の工数を大幅に削減できます。
設計業務にAIを活用する利点
設計業務にAIを導入することには、数多くの利点があります。
まず最大のメリットは、業務の効率化と品質の両立です。従来、設計業務には膨大な知識と経験が求められ、それをもとに仕様を読み解き、図面や設計資料を作成するには多くの時間と工数がかかっていました。
しかし、ChatGPTのような自然言語処理AIは、関連資料からの情報抽出や過去の設計実績との比較や、技術文書の要約といった作業を自動でこなせます。従って、設計者の負担を大きく軽減できます。
また、設計の妥当性確認やレビューの支援も可能です。たとえば、設計意図や変更理由をAIが文書化することで、レビュー担当者が意図を正確に把握しやすくなり、コミュニケーションロスの削減につながります。さらに、社内FAQ対応や部品の流用可否の判定などもAIに任せることで、属人化しがちなナレッジの共有が促進され、業務の標準化・平準化が実現します。
新入社員や若手技術者の育成にもAIは大きな効果を発揮します。先輩設計者に聞くまでもないが調べるには時間がかかるような疑問に対し、AIが即座に回答することで、学習スピードを高め、早期の戦力化が期待できます。
さらに、言語化が苦手な設計者でも、ChatGPTなどのAIツールを用いることで設計ドキュメントや仕様説明文をスムーズに作成でき、報告・共有の精度が向上します。
このように、AIの活用は単なる業務支援にとどまらず、設計現場全体の知的生産性を底上げし、組織全体の競争力強化につながる可能性を秘めています。
お客様の声から、もっと業種別に学んでみよう!
製造業の図面・文書管理 自治体の完成図書管理
D-QUICK導入事例集
設計業務にAIを活用する時の課題
設計業務におけるAI活用は多くの利点をもたらす一方で、慎重な対応が求められる課題も存在します。
まず最も重要なのは、AIの出力結果に対する信頼性です。ChatGPTをはじめとする生成系AIは、あたかも正しそうな文章を滑らかに生成しますが、必ずしも事実に基づいているとは限りません。特に技術的な設計判断や法規制に関わる事項では、誤った情報に基づいて意思決定をしてしまうリスクがあり、AIの回答をそのまま鵜呑みにせず、設計者が裏付けを取りながら活用する姿勢が必要です。
次に、情報漏洩リスクの問題も軽視できません。設計に関するデータは企業にとって機密性の高い資産であり、外部クラウドのAIに入力することで意図せぬ情報流出のリスクが生じます。このため、AIの活用にあたっては、社内サーバー上での運用、セキュリティを確保した専用クラウドの使用、あるいは機密情報の匿名化といった対策が不可欠となります。
さらに、AIの導入と活用には、技術的な整備だけでなく運用面での工夫も求められます。たとえば、設計者が使いやすいインターフェースの設計や、業務に即したテンプレートの整備がされていなければ、ツールがあっても現場での定着は難しいでしょう。また、AIの回答が誤っている場合や、意図通りの結果が出ない場合に、ユーザーがどのように判断・対応するかの教育も必要です。
このように、AI導入には技術・情報・人材の各側面で課題があります。しかし、これらを事前に把握し適切に対応することで、リスクを最小限に抑えながらAI活用のメリットを最大限に引き出すことが可能です。
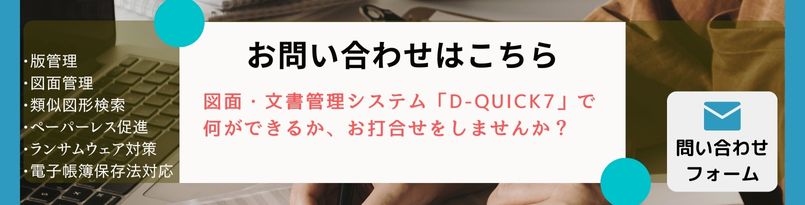
まとめ
製造業における設計業務のAI活用と、利点や懸念点について説明させていただきました。AIを適切に活用することで、本来設計者が時間を割くべきコアとなる業務へ集中することができ、業務効率化や生産性の向上が見込めます。
当社ではAIの力を活かしながら、図面情報の整理や共有、ナレッジ継承を支援する「図面管理システム」をご提供しています。設計業務の属人化や情報検索の手間に課題を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。製造業のAIを活用した設計業務の対応方法をご提案いたします。
まだ情報収集レベルで、学びを優先されたい方
「図面・文書管理で困ったときのハンドブック」~製造業・完成図書・テレワーク・クラウド、すべての解決策をお見せします~
システムやクラウドサービス等の具体的な解決策を探している方
図面・文書管理システム「D-QUICKシリーズ」基本ガイドブック
版管理や採番に課題を感じている方
版管理と採番管理を解決する D-QUICK7機能ガイド
より詳しい事例を知りたい方
「製造業の図面・文書管理 自治体の完成図書管理 D-QUICK導入事例集」
安心・安全に図面・文書管理を行うためのポイントが理解できる資料になっています。 ぜひ、ダウンロードページより資料をご覧ください。
「文書管理ノウハウ」の関連ブログ
- 製造業DXが進まない本当の理由 成功に導くヒントをご紹介
- 文書管理システムで実現するグローバルオペレーションの効率化
- AIで図面管理を実現する2つのキーワード セマンティック検索も解説
- 出図とは?最新版の混乱をなくす出図管理の基本と効率化のコツ
- 文書管理の原点「ドキュメント」とは?現場で活かす価値も解説
- 設計 ・ 仕様書を含む契約書管理の課題を解決する効率的な方法
- 文書管理で原本を守る 文書管理システムとファイルサーバーの違いを解説
- 製造業DXの事例 課題と推進させるポイントをご紹介
- 製造現場の未来を拓く 図面のペーパーレス化がもたらす3つの革新
- 図面管理システムで始める完成図書のデジタル化
- AIで製造業の設計業務はどう変わる?課題と対応方法を解説
- ファイルサーバと同じ操作性を持つ検索ツールで効率化!基幹システム刷新のポイントを解説
- PL法で問われる証拠力、文書管理の重要性を徹底解説
- 機密情報を守り情報漏洩を防ぐ方法 図面・完成図書はどうする?
- フォルダ検索したい!なぜ目的のフォルダが見つからないの?
- ナンバーの付け方で劇的に変わる 文書管理の業務効率アップ術
- ナレッジマネジメントとは?情報の属人化を解決するシステムへ
- バックオフィスの文書管理の課題とは?システムが必要な理由を解説
- 書類の電子化をしよう!方法と注意点、事例をご紹介
- 文書管理されるファイルは保存?格納?違いや意味を理解してみよう